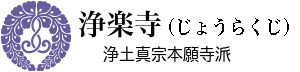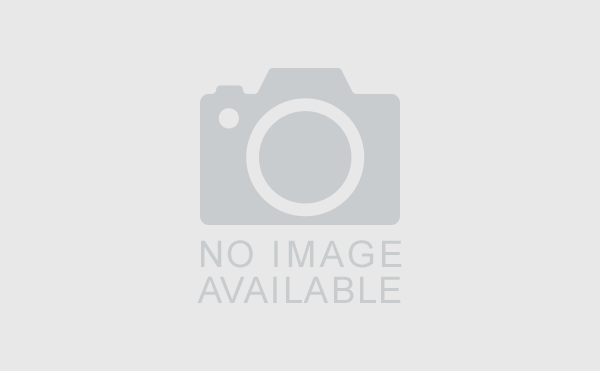春彼岸法要

春彼岸法要を3月21日(昼座13時30分、夜座19時30分)、3月22日(昼座13時30分)に勤めさせていただきました。ご参拝の皆さまとお正信偈をお勤めした後、ご法話をいただきました。
春彼岸法要と秋彼岸法要では前住職からご法話をいただいております。はじめに、お彼岸、此の岸や彼の岸、ご先祖様、「暑さ寒さも彼岸まで」などを仏教の教えとしてお話いただきました。そしていつも通り、各座で昔話を取り上げ、そのあらすじを簡単にご説明いただいた後、そこから教えられる事や仏様からのお話として捉えてみようという事を行いました。(前住職によると「あくまで私自身の解釈ですが…」とのことです)
今回の春彼岸法要では、
「天狗のかくれみの」
「海の水はなぜ塩からい」
「おならの商売」
のお話をいただきました。
●天狗のかくれみの
彦八という男がいました。その彦八は「山にいる天狗が被ると姿を消す事ができる「隠れ蓑」を持っているらしい」と聞きつけ、それが欲しくてたまらなくなりました。知恵者の彦八は山へ出向いたが、隠れ蓑を被っている天狗は見えません。どうにかならないかと思案した挙句、竹筒を取り出し目にあてて「山の麓がよく見えるよく見える、その先には京の都も見える、お祭りでもしているようだ」と大きな声で言いました。すると興味を持った天狗が出てきたのか「ワシにも見せてくれ」と声がしました。彦八と天狗は話し合いの末、竹筒と隠れ蓑を少しの間交換することになりました。騙された天狗は時遅し、隠れ蓑を被って姿を消した彦八は山を降りて行きました。
姿が見えない事をいいことに、町の中でいたずらのし放題、そして家に帰りました。翌朝、起きてみるとその隠れ蓑がありません。彦八の女房曰く「古くて汚い蓑だったので燃やした」との事。残念がる彦八だが「燃やして灰になっても姿を消す事ができるのでは」と思い、裸になって体に塗ってみたところ姿を消すことに成功。そして今日も町でいたずらのし放題。団子屋さんで無銭飲食した後、口の周りについた団子の餡を舌先できれいにすると、そこだけ灰が取れて口先だけが現れました。おかしく思った町人から追いかけられ逃げようとすると汗をかき、降ってきた雨とともに灰が取れだんだんと裸の姿が見えてきました。町でのいたずらが彦八の仕業とわかり罰として袋叩きに。その後反省した彦八は許してもらえました。
この昔話からは、彦八だけでなくみんな隠れ蓑を持っている、どういう隠れ蓑かを「身口意の三業」の説明とともに、そして正しい事を教えてくださる為に蓑を外してくれた雨が仏様の慈悲ではないか、彦八は私自身ではないか、と捉えてみようとお話いただきました。
●海の水はなぜ塩からい
ある村に兄弟が住んでおりました。その村では飢饉になり村人が飢えていました。優しい兄は食べ物を分け与えていましたが、弟は「自分たちも飢えてしまう」と反対していました。いよいよ自分たちが食べるものがなくなってくると弟は最後にかき集めたそば粉をまるめて団子にし家を飛び出してしまいました。兄は団子1つとともにそこに留まり家の近くをぶらぶらしていました。大きな石の上へ腰掛け団子を置くと、石に開いていた穴に落ち込んでしまいました。落ち込んだ先はみんな裕福な小人の世界でした。小人からその団子が欲しいと言われた兄、自分の食べ物がなくなるが小人に与えてしまいました。そのお礼に小人から大きな石臼をもらい「欲しいものを言って右に回すとそのものが出てくる、左に回すと止まる」と説明を受けました。家に帰ってお腹が空いた兄は「おにぎり」を出しました。その後いろいろな物を出しては村人に分け与えました。そんな状況を知った弟はその石臼を奪い逃げてしまいました。自分が生まれ育った土地を捨て船で逃げました。その途中、持っていたそばを食べる為に石臼で塩を出しました。ところが止め方を知らない弟、石臼とともに海に沈んでしまいました。今でも石臼から塩が出続けており、海の水が塩辛くなったそうです。
この昔話からは、施せる人間と自分の欲を満たすだけの人間、我執について、幸せと不幸とは、弟の留めない我執として止まらない塩が表現、兄の村人への限りない施しが仏教の世界を表現しているのではないか、と捉えてみようとお話いただきました。
●おならの商売
昨年の春彼岸法要でお話しいただいた昔話「鳥のみじい」を再度聞かせていただきました。
面白いあらすじながら、「現在の状態を受け入れ生きていくのはどういうことなのか」をお話しいただき、大切にしていかないといけない事などを考えさせられました。
あらすじなど詳細は、昨年の春彼岸法要の活動報告
https://johrakuji.jp/2024/03/25/haru_higanhoyo-2/
をご参考ください。
前住職による昔話法話。
毎回おもしろおかしく、またハッとするような気づきや為になる話を聞かせてもらっています。次回は秋彼岸法要でお話しいただく予定です。是非ご参拝ください。